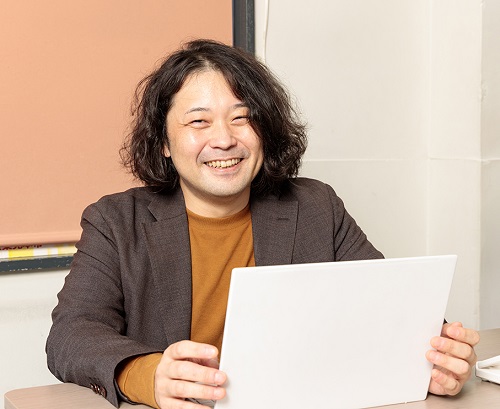「Webサイトを作れば、お客さんが勝手に集まってくる」
「Webサイトは24時間働く営業パーソン」
「いままで買ったことがないお客様がなにもしないでも集まってくる」
Webサイトの制作サービスを自身で展開している経験上、Webサイトに関するお問い合わせをたくさんいただきます。その中のうち、「Web集客ができるWebサイトをつくりたい」といったお問い合わせが大体4割くらいといった印象。
ですが、一概にその期待にこたえられるわけではありません。ビジネスの種類、従来の販売方法、そしてなにより商品やサービスの対象となるお客様の性質や行動特性により、Web集客がうまくいく場合とそうでない場合があります。
統計によれば、日本国内だけでも年間30万以上の新規ウェブサイトが立ち上げられていると言われています。この中で選ばれるWebサイトを作るのは容易ではありません。
Webサイトを公開したものの、思うように成果が上がらず、疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。ある調査では、中小企業のウェブサイトの約70%が「期待した成果を得られていない」と回答しています。
ではWebサイトは役に立たないのでしょうか?そんなこともありません。適切な役割をWebサイトに持たせることでしっかりと機能します。
この記事では、多くの人が勘違いしやすいWeb集客の本質について掘り下げていきます。
集客の定義を間違えている
まず、多くの人が「集客」という言葉の定義を誤解しています。
「集客」とは単に「人を集める」ことではありません。デジタルマーケティングにおける真の集客とは、「自社の商品やサービスを必要としている潜在顧客・見込み客を集め、関係構築を始めるきっかけをつくる」ことを意味していると考えています。
つまり、サイトへの訪問者数(アクセス数)が多くなれば成功というわけではないのです。
例えば、私が支援を始める前の会社では月間の訪問者数だけをモニタリングしていました。
ですが、仮に月間10万人が訪問するサイトがあっても、その訪問者があなたのビジネスと何の関連もない層であれば、ビジネス的な価値はほとんどないといっても過言ではありません。
一方で、月間1,000人が訪問するサイトでも、その全員があなたのサービスを切実に必要としている人であれば、大きな成果につながる可能性があります。
私が以前支援したノベルティグッズ販売会社のケースでは、ブログを使ったSEO(検索エンジン最適化)対策がうまくいき、法人の中では比較的アクセスの多い、月間10,000人が訪問するサイトにまで育ちました。ですが、実際に見積もりや問い合わせは月間1件、多くても2件程度でした。
企業側の感覚としては「これだけアクセスがあるのに」、といったもの。依頼され、アクセスを分析し、原因を調査しました。
訪問者の多くは、「光るノベルティ」や「シーズンもののノベルティ」や「推し活ノベルティ」といった情報収集を目的としていたため、ブログの記事だけ見て満足し、他のページをまったく見ていないことがわかりました。さらに記事単体の品質が高いことで、訪問者は満足し、記事自体は評価され上位表示されるようになっていて、アクセスは伸びていたもののビジネスにとっては「役に立たない高品質コンテンツ」が大量に存在することになりました。
SEO対策の考え方として、検索数が多いキーワードから対策するということがあります。これ自体は間違っていないのですが、それでアクセスが増えたからといってお問い合わせにつながらないのであればWebサイトとして機能しているかというと疑問です。
この企業の強みはノベルティグッズの企画や、安定的な製造ができること。そうであるなら、オリジナルノベルティグッズの発注のポイントや、グッズを企画するときの注意点などを伝える記事を書いたほうが良いとお伝えし、方針・ターゲットを変更していただきました。他の部分の改修もすることで問い合わせは多いときで月10件弱ほどに増えました。
このようにアクセスの「質」の部分を見落としてしまい、アクセスの「量」だけを追い求めてしまうことが、多くの企業のWeb集客におけるつまずきと考えています。
Webサイトを「見た」だけで買う人はほとんどいない
もう一つの大きな勘違いと考えられるのは、「Webサイトを見た人がすぐに購入してくれる」というものです。実際には、法人であれ、個人であれ購買行動はそれほど単純ではありません。
Webサイト制作で何かを売ると考えたとき、ECサイト(楽天やAmazonのような商品を購入するためのサイト)のようなものをイメージされることが多いのですが、商品をネットという販路で販売する企業以外はこのようなイメージを持つことはあまりよくありません。
ECサイトに訪れる人は何かを買おうと思っているため購買意欲がすでに形成されています。ですが、「買おう」と思っていただくまでに説明や説得が必要な商品やサービスの場合、ECサイトのようなモデルで考えてしまうとまったくうまくいきません。
デジタルマーケティングの世界では「AISAS(アイサス)」という購買行動モデルがよく知られています。これは「Attention(注意)→Interest(興味)→Search(検索)→Action(行動)→Share(共有)」というプロセスを表しています。
様々な考え方や、モデルはありますが、何かを買おうとする前に、必ず調べて、比較検討するということは意識する必要があります。
デジタルマーケティングでは「衝動買い」を期待するのは難しく、また「衝動買い」させるためには商品性に加えて、高度なテクニックが必要になります。
あるとしたら、美容・健康系のグッズやサプリくらいでしょうか。
具体的に考えてみましょう。
例えば、あなたが新しいパソコンを購入するとします。
- 広告や口コミで知る(注意:Attention)
- 自分の用途に合うか、商品の特長を調べる(興味:Interest)
- 他にいい商品がないか、複数の機種を比較検討するために情報を検索する、その過程で自分なりの判断基準(機能なのか価格なのか)を形成する(検索:Search)
- 実際に店舗で確認し購買、もしくはオンラインで購入(行動:Action)
- 購入後に口コミやSNSで感想をシェアする(共有:Share)
というプロセスを経るでしょう。
この記事をご覧の方の商品・サービスも上記のモデルに当てはめて考えてみてください。前にも書きましたが必ず比較検討はされてしまいます。
さらに、調査によると一般的な消費者は購入前に平均7回以上のタッチポイント(企業との接点)を持つと言われています。
これは業種によって異なりますが、BtoCビジネスでは平均8回、BtoBビジネスでは平均11回のタッチポイントがあると報告されています。つまり、あなたのWebサイトを訪れた人がいきなり商品を購入することはほとんどないのです。
デジタルマーケティングで売るのが難しいビジネスの一つに無形サービスや予防的なサービスがあります。コンサルティングや研修などのサービスをイメージしてください。そもそも、課題が形成されていることが少ないという別の問題があるのですが、かりに課題に気づいた潜在顧客が検索でサービスをたまたま見つけてもらえたとします。
しかし、すぐに契約することはなく、Webサイトをこまかくチェックし、価格の相場感などを調べ、ブログ記事を読んだり、資料をダウンロードしたり、メルマガに登録したり、無料セミナーに参加したりと、オンライン・オフライン問わずタッチポイントが徐々に増えて、購買意欲が高まり、十分な信頼関係が築かれた後に初めて契約に至るのです。
実際のデータを見ると、上記に書いたような「買いたい」と思って訪れるオンラインショップの平均コンバージョン率(訪問者が購入に至る割合)は約1〜3%と言われています。つまり、ほとんどの訪問者はすぐには購入しないのです。さらに、初回訪問で購入する人の割合はさらに低く、多くの場合1%未満とされています。
ECサイトでない場合は1000人アクセスがあってようやく1人問い合わせがあるかないかという印象もあります。その場合も複数回訪問してからのものになります。
Webサイトの本当の役割とは
ではWebサイトの真の役割は何でしょうか?
それは「リアルの営業活動を楽にすること」と「見込み客から信頼を得るためのベースキャンプ」だと私は考えています。
冒頭に書いたような、「Webサイトは24時間働く営業パーソン」というのは厳密には間違っていると考えています。
24時間365日、本当にあなたの代わりに営業活動を行ってくれるでしょうか。経営者や、社内のトップセールスと同じ役割を果たせるでしょうか。
実際の営業現場でも相手の出方を見ながらトークの内容・順番を変えるはずです。身振り手振りを加え、表情・トーンを工夫してようやく売れるはずです。ですが、Webサイトでは伝える内容も順番も事前に決められたものです。今後の技術発展で改善余地はあるとはいえ、それでも人間の営業には勝てないと考えています。
ですから、あくまで見込み客との関係構築を促進し、リアルの営業活動を補助する役割を果たさせることが重要だといえます。
例えば、必ず営業の現場で話すこと、いつも聞かれること、お客様が疑問に思いそうなこと、それをすべてWebサイトに記載しておくのです。
私のデジタルマーケティングの師匠が「情報の先出し」が重要だとおっしゃっていました。何かを購入してもらうためには、すべての不安や疑問を払拭させる必要がある。ですが、実際の営業現場ではそれをすべて伝えきることも難しい。そのためWebサイトを通じて、「情報を先出し」し、いわば見込み客に予習・復習させるための場として使うべきだということです。
あるITサービス企業にいたとき、Webサイトに見込み客が知りたい情報をほぼすべて盛り込み、また営業現場で聞かれたことをすべてサイトに反映していました。またいわゆる「教育型のコンテンツ」で充実させることで、見込み客が事前に製品知識や製品の選定基準を持った状態で商談に臨むようになりました。さらに営業対応する人間のプロフィールなども事前に開示しました。
このような活動を地道に行ったところ、初回問い合わせから申込まで40日程度かかっていたのが20日程度まで短縮、問い合わせからの申込率が20%弱だったものが40%を超えるようになりました。
また、Webサイトは「見込み客から信頼を得るためのベースキャンプ」だと考えています。訪問者や見込み客は「この会社は信頼できるか?」「本当に自分の問題を解決してくれるのか?」といった疑問を持っています。見込み客は自社と他社を相対的に比較検討するだけでなく、自社自身のこともWebサイトをくまなく見て信頼に値するのかを評価するのです。
役に立つWebサイトはこれらの不安を適切に解消します。デジタルマーケティングの最大の目的は、もちろん売上向上ですが、ネットという閲覧・クリックだけで済む世界から、リアルの問い合わせなどの行動につなげることだと考えています。このステップへ進む心理的なハードルを下げる役割としてWebサイトを機能させることが重要です。
多くの企業の分析をしていて気がついたことがあります。実は問い合わせや、見積もりをしたあとのほうが会社概要や代表者挨拶など会社の情報を調べる方が多いということです。本当に問い合わせしてよかったのかという不安を取り除くためにどのような会社なのかを知りたくなるのだと考えています。
このときに会社の住所と地図しかなかったら、もしかしたら問い合わせしても実際の面談のキャンセルなどにつながるかもしれません。
今回はWeb集客に関する「間違った」認識についてと、Webサイトの本当の役割についてお伝えしました。Webサイトを使って何かを売ろうとする場合も、通常の営業活動と同じように工夫やしかけが必要であり、Webサイトがあるだけでは売れないのです。
次回はこの前提をふまえた上で、具体的なWeb集客のポイントについてお伝えいたします。