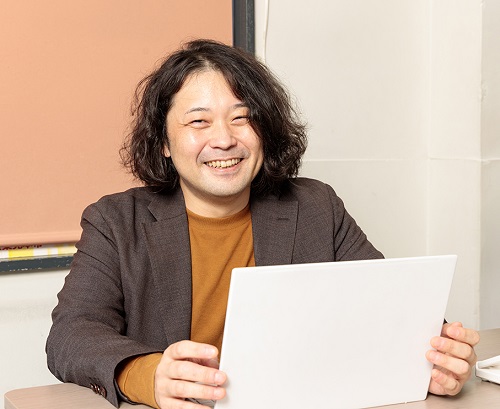実際の現場からわかるデジタルマーケティングの現実
前回は、デジタルマーケティングに関する代表的な誤解について説明しました。
「すぐに効果が出る」「低コストで成果が得られる」「誰でも簡単にできる」といった期待が、なぜ現実的ではないのか、イメージをしていただけたことと思います。
前回の内容をふまえて、自身の実践経験や、実際の支援現場で見えてきたデジタルマーケティングの現実をお伝えし、本当に成果を出すために必要な取組取り組みについても具体的にお伝えしていきます。
現実1:地道な努力と継続が必要
デジタルマーケティングで成果を出すためには、仮説に基づく戦略と迅速な実行、実行に基づく仮説・戦略の見直しの「繰り返し」が必要です。
一度の投稿や短期キャンペーンで劇的な結果を得ることは稀です。
また仮に成果が出たとしても「たまたま」の可能性もあり、継続的な成果に結びつけるのは困難です。
例えば、ユーザーにとって有益なコンテンツを発信しつづけ、そこから自社のファンになってもらったり、サービスの購入につなげたりするための施策である、コンテンツマーケティングという手法では、「コンテンツの複利効果」という概念があります。
これは、質の高いコンテンツを継続的に発信することで、時間の経過とともに総合的な効果が指数関数的に高まるというものです。しかし、この効果が現れるまでには、多くの場合6ヶ月から1年以上の地道な活動が必要です。
これまでの経験上では地道なコンテンツの追加は、1ヶ月は継続できても、3ヶ月続けることは難しい場合がほとんどです。コンテンツを制作する担当者もなかなか成果がでない状況に焦りを覚えたり、社内の理解が不足していて「意味ない」と思われることによる重圧などで継続できなかったりと企業で地道な努力を続けるのは難しいといえます。特に、前述の「すぐに結果が出る」という誤解を、社長や責任者がもっていると施策の継続が難しい状況になります。
現実2:正しい計測と改善のサイクルが重要
デジタルマーケティングの大きな利点のひとつは、勘に基づくものではなく、データに基づいた改善が可能な点です。例えばWebサイトを訪れた人はどのような人なのか、どこからサイトに訪れたのか、どのような行動をとったのかなどのデータが収集されます。
ですが、データを収集するだけでなく、適切な目標や評価指標を設定し、継続的に分析・改善することが求められます。
多くの企業が陥ることとして、「見栄えの良い数字」に注目してしまうことです。
例えば、Webサイトの訪問者数やSNSのいいね数は増えていても、実際の売上や見込み客獲得につながっていないケースは少なくありません。
企業を支援していて、サイトの閲覧数が増えたということが社内での報告対象になっていることもありますが、そこから売上にどれだけつながっているかをお聞きすると途端にトーンダウンされることもあります。
効果的な測定と改善には以下のようなステップが必要です。
- ビジネス目標に関連度の高い指標の設定
→この指標がよくなれば売上が増える、見込み客数が増えるといった関係性がある指標で施策を評価することが重要です - 適切な分析ツールの導入と正確なデータ収集
→正しい現状を認識することが改善の大前提です - 定期的なデータ分析と変化があった場合の原因の考察
→データを収集するだけでなく、なぜ数値に変化があったのか、意図したものかそうでないのかなどの原因を考えることが重要です - 施策の調整と最適化
→よくなっても悪くなっても打っている施策の評価が必要です - 結果の確認と再評価
→サイトの結果と売上や見込み客数などビジネス目標が連動しているか、連動していないのであれば1の指標の見直しを含めた改善が必要になります
現実3:統合的なアプローチが成功の鍵
デジタルマーケティングでいうと、「Webだけ」で売上が増える、お客様が増えるという誤解もありますが、企業のマーケティング・営業活動全体を俯瞰すれば、もちろん単独で機能するものではありません。
Webだけを切り離して考えるのではなく、企業としての総合的なマーケティング戦略の一部として機能させることが重要です。
オンラインだけでなく、リアルの施策を連携させ、お客様の購買体験をより快適にするアプローチが必要です。
例えば、以下のような連携が効果的です。
- 実店舗でのQRコード表示によるオンラインへの誘導
→誘導先にお客様が知りたい情報が満遍なくあるか? - オンライン広告とリアル広告のメッセージ一貫性
→ブランディングという言葉は多義的ですが、メッセージや訴求が一貫していることもブランディングとして重要です。例えば、チラシでは高品質を売りにしているのに、オンライン広告では安さを売りにするとなど、両方のメッセージを受け取った方は混乱してしまう上にのと信頼性を損ねます。 - カスタマーサポートとSNSでの顧客対応の連携
→カスタマーサポートでお問い合わせが多い内容はSNSなどでも発信すべきですし、SNSでもお問い合わせ対応するなど、お客様がよりよい体験をするためにはどうすればいいのかという考えに基づき、最適な情報発信をする必要があります。
デジタルマーケティングを成功させるために
1.現実的な期待と長期的な視点を持とう
デジタルマーケティングはすぐに売上が急増するものではなく、時間をかけて顧客との関係を築き、価値を届けるためのものです。その意味では、リアルのマーケティング施策と変わることはありません。
売上に直結することはすぐには難しくても、達成すべき目標は段階的に変わり、その目標を達成していくことで少しずつ売上に寄与する部分が出てきます。
3ヶ月、半年、1年、そして3年先を見据えた目標を立てましょう。日々の数字に一喜一憂するのではなく、長い目で見て育てていくという視点を持つことが大切です。
打った施策の結果が一般的にはやくでやすいデジタルマーケティングとはいえ、閲覧するユーザーと信頼関係を構築し、お客様になっていただくという「結果」を出すためにはリアルの施策と同じくらいに時間がかかります。
短期的には目に見える成果が少なくても、継続的な取り組みが将来的な顧客を創造したり、コンテンツの信頼性や口コミとしての効果につながっていくことを忘れないでください。
そのためにも、各時間軸での現実的な中間目標を設定し、一歩一歩着実に進んでいきましょう。
企業支援していて一番もったいないと思うのが、途中で諦めてしまうことです。デジタルマーケティングの領域以外で売上を担保できている企業においてはその傾向が特に顕著です。ただ、デジタルマーケティングで築いたものは確実に企業にとっての大きな資産になります。
2.お客様目線を忘れずに
デジタルマーケティングの世界は日進月歩であり、最新技術や新しいプラットフォーム、新しい媒体(SNSなど)に目を奪われがちです。
大切なのは「顧客が何を求めているか」「その顧客はどこにいるか」です。
どれだけ自分たちが「いいコンテンツ」であったと思っても、お客様の悩みを解決したり、価値を届けられたりしなければ意味がありません。
また新しいプラットフォームや媒体に手を出したとしても、そこにあなたのお客様になりうる人がいるかどうかは別の問題です。
自社のターゲットとなるお客様のことをとことん理解し、彼らの抱える問題や願望に応えるコンテンツや、情報発信の体制構築に力を注ぐことが重要です。
そのためには、なぜ自社を選んでくれたのかを、顧客インタビューやアンケート調査、SNSでの声の収集などを通じて、お客様の本音を探り、それに応えるコンテンツを作り続けることが重要です。表面的なニーズだけでなく、顧客が言葉にしていない・できていない潜在的な課題にも目を向けることで、よりお客様に役立つコンテンツを届けることが可能になります。
また、新しいSNSが出てきたからといって、とりあえず飛びつくことも避けるべきだと考えています。ここ数年でも新しいSNS媒体が複数でてきましたが、今でも継続して残っていて、ビジネスとして役立ちそうなのは数少ない状況です。
新しいことをすればいいというわけではありません。お客様が知りたい情報を、どのような手段で伝えるのが最適なのかを考え続ける必要があります。新しいものに飛びついたばかりに既存の施策がおざなりになっては本末転倒です。
よくあるのが知り合いの会社が〇〇やってるからやってみたい、というもの。本当に意味があるのか、具体的にはその知り合いの会社とのビジネスの種類やお客様の属性は同じなのかを見極めて始めることをおすすめします。
3.少しずつ学び、実践を重ねよう
デジタルマーケティングの全てを一度に習得・実施しようとするのは現実的ではありません。まずは自社の状況や目標に最も合ったチャネルや手法から始めて、少しずつ範囲を広げていくのがベストです。
例えば、最初はSEOに注力し、自社サイトの基盤を固めることから始めるのも一つの方法です。ある程度軌道に乗ったら、SNSマーケティングやメールマーケティングなど、他の手法に展開していきましょう。短期的に結果を見たいのであれば、Web広告になりますが、必ずしもそれが正解とも限りません。
小さな実験と検証を繰り返しながら、自社らしいデジタルマーケティングの勝ちパターンを見つけていくことが重要です。
支援を通じてよく申し上げるのが、「初期仮説」は多くの場合間違っています。間違っていても修正がすぐに可能なのがデジタルマーケティングのいいところでもあります。
失敗したという事象にとらわれず、常に「学びの姿勢」を持ち改善を続けることが成功への近道です。
デジタルマーケティングの世界は日々変化していますが、その変化に振り回されるのではなく、基本的には顧客中心の考え方を軸に、顧客のために新しい技術やトレンドを取り入れていくという感覚を持つことが大切です。
一つひとつの施策から得られた気づきを次に活かし、PDCAをまわしながら、螺旋状に成長していくプロセスが重要です。
まとめ
デジタルマーケティングは確かに強力な武器になりますが、持っているだけですぐに効果を得られるような「魔法の杖」ではありません。
短期間で劇的な効果を期待するのではなく、長期的な視点での戦略立案と地道な実行が成功への道です。
デジタルマーケティングのことを理解し、施策に対する適切な期待値を持ちながら、顧客中心のアプローチで継続的に改善を重ねることで、デジタルマーケティングは企業の成長を支える重要な柱となるでしょう。
「魔法」を期待するのではなく、デジタルデータに基づいた現状の正確な把握をベースに、根拠のない勘ではなくデータを基にした創造的な発想で、取組を続けていきましょう。