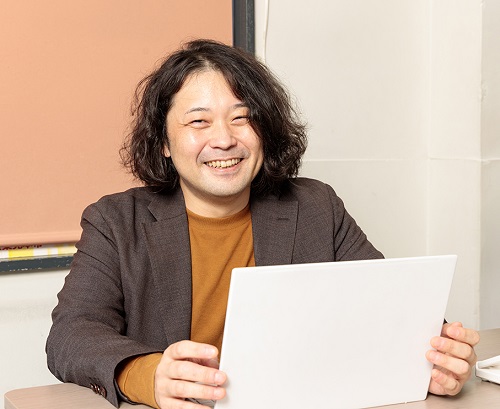前回の記事では、多くの人が勘違いしやすいWeb集客についてお伝えいたしました。
本記事では具体的なWeb集客の手法と、実践方法、成功事例をお伝えいたします。
Web集客は合せ技
「自社の商品やサービスを必要としている潜在顧客・見込み客を集め、関係構築を始めるきっかけをつくる」ためのWeb集客のポイントをお伝えします。
まず大前提として、一つの施策だけでうまくいくことはありません。複数の施策を組み合わせることでようやくWeb集客は成功に近づきます。
マーケティングの全体設計を意識する
商品・サービスを認知し注意をはらってもらうことは一番コストかかるといわれてますが、認知はマーケティング活動の入口に過ぎません。先ほどの「Attention(注意)→Interest(興味)→Search(検索)→Action(行動)→Share(共有)」モデルを参考に、各段階で適切なコンテンツやアプローチを用意することが重要です。
私は上記モデルをベースに
認知(知ってもらう)→興味(自社のよさを知ってもらう)→比較検討(検索含めた比較により他社ではなく自社が選ばれる理由を知ってもらう)→背中押し(行動するためのハードルを取り除く)→行動(問い合わせ・見積もりなどのリアルな行動をしてもらう)
という型を使ってコンテンツや設計を行っています。
例えば、ある健康系の商品の場合は下記のようにしています。
- 認知 :短期的にはWeb広告をメインにする。中期的に、広告の運用や実際のお客様からの申込をベースにコンテンツを改良し、SEO対策を行う。リソースの問題からSNSからの認知を狙わない(運用をしない)
- 興味 :製品の特長を顧客のニーズに合わせて訴求する
- 比較検討:記事を使った商品選定のポイント・事例紹介・比較表・お客様の声
- 背中押し:特典・キャンペーン
- 行動 :お問い合わせフォームの入力を少なく・わからないことがあれば電話に誘導
複数の接点を用意する
Webサイトだけでなく、SNS、メールマガジン、ブログ、動画、LINE公式アカウント、ポッドキャスト、オンラインセミナーなど、様々な接点を用意することも重要です。
ここで大事なことは、関係性を深める手段と集客のための手段を混同しないことです。
例えばSNSからの集客を見込んでなくあくまで最新情報や事例の紹介のために使っているのに新規集客が少ないと考える方もいらっしゃいます。あくまで、手段ごとの目的を明確に認識しておきましょう。それ以外の目的をもたせると必ず運用段階で失敗します。
複数の場所で、仮に同じ情報であっても伝えつづけることで見込み客との関係を深めていくことができます。
ある製造メーカーの支援事例では、Instagramではお客様の声中心、YouTubeでは使い方の紹介、メールマガジンでは定期キャンペーンと会社の情報・代表の取組の紹介など各手段のコンテンツを切り分け、それぞれのメディア特性に合ったコンテンツを発信しています。
今までは同じ情報をすべてのメディアで流すだけでしたが意図してコンテンツを使い分けることで、他の施策とも相まって売上が2.7倍になりました。
やらないことを決めることも重要です。この会社ではX(旧Twitter)は顧客属性的に合わないということでやらないという方針にしました。
リードナーチャリングを実践する
見込み顧客(リード)に対して知りたい情報を伝え、いわば「育成」して購買意欲を高め商談や受注につなげる手法をリードナーチャリングといいます。
ご自身で情報をすべて取ってくださる方ですと商談はかなり楽なのですが、そのような方ばかりではありません。ハードルの低い無料のコンテンツ(選定のポイント・比較表・お役立ち資料など)を提供してまずはメールアドレスやLINEアカウントだけを取得することを考えましょう。少しでも興味を持った方が、購買という行動はまだ起こさないまでも、しかるべきタイミングで購入していただけるよう、メールアドレスなどを取得しておくことが重要です。
また単純接触効果という概念もあります。単純接触効果とは、特定の物事に対して繰り返し接触することで、好印象を持つようになる心理的現象をいい、接触頻度を増やすことで親近感を持ってもらうことをメールマガジンの定期的な運用で実現することができます。
メールアドレスを取得して定期的に有益コンテンツを配信することは関係性構築のためにも重要です。
研修会社の支援では、いきなり社員研修や幹部研修などの申込は難しいと判断。「マネジメント層育成のための10のポイント」というコンテンツをメールマガジン形式で提供。これまでサイトからの問い合わせの数が大体1000人の来訪があって1人からお問い合わせいただく(問い合わせ率が0.1%)程度でした。1000人に1人しか企業に接触しようと思わなかったということです。
ですが、申込や問い合わせといった行動よりもハードルの低いメールマガジンの登録という行動の出口を用意したところ、メールマガジンへの登録が1000人に30人、(登録率3%)に改善。何かしら行動しようとする人が大幅に増えました。メールマガジンでは、毎回無料相談へ誘導。無料相談への申込がメルマガ登録者の10%程度あったので、1000人に30人がメールマガジンに登録し、その中の3人を無料相談という企業側への自発的なコンタクトをさせることに成功。単純計算で1000人に1人から1000人に3人に増えたということで、行動の数を3倍率にすることができました。
もちろん、ただ数が増えただけでなく、メールマガジンなどで事前にしっかりと情報を知った上でのコンタクトなので、質の高い見込み客と商談をすることができました。
顧客の声はなぜ大事なのか
顧客の声や事例が重要だと言われますが、2つのポイントで重要です。
まず、閲覧している見込み客にも属性というか、理解のクセのようなものがあります。具体的な事例などがあったほうが理解が進む方と、抽象的もしくは感情的な訴求だけで理解をしてくれる方に大きくわかれます。前者の見込み客の場合、他社がどのように取り組んでいるかなどをつたえることが重要な説得材料になります。
顧客の声が一定程度あるということ自体が信頼感の根拠になりえます。はじめて買う商品や、はじめて取引する会社について他にもお客様がすでにいるということを伝えること自体が重要になるのです。
例えば、広告でも数字や成果を伝えることがありますが、事例を使って伝えたほうが見込み客を納得させる効果が高い場合があります。
とあるBtoBサービス企業では、詳細な導入事例を掲載し、導入検討企業の社内決裁のための資料に添付する参考事例などを載せ始めてから、問い合わせの質が向上したということもありました。
実際の成功具体例
塗装技術のBtoB向けサービスを新しく展開した事例を具体例としてお伝えします。
営業リソースの問題から、WebサイトだけでWeb集客を目指していましたが、苦戦していました。当初のアクセスはほぼゼロ。問い合わせも当然ないという状況でした。
しかし、戦略を立案し、以下のようなアプローチに変更しました。
- 塗装素材に関するワードについて詳細説明ページを作る
- 塗装に関する専門家という立ち位置を明確にして強み・選ばれる理由を伝える
- 得意な技術に関するノウハウ記事を作成
- 今までの実績をベースに事例を10事例載せる(少しずつ増やす)
- よくある質問ではなく、「このような依頼にもこたえられますページ」をお客様からの問い合わせベースで増やす
- 各SNSで塗装に関する動画を配信
- チェックポイントの資料をダウンロードさせメールマガジンを配信。メルマガでは上記の対応できる依頼についての詳細を配信
- Webサイトにほぼすべての情報を開示しているので商談もスムーズに進み月によってはほぼ成約
この結果、ウェブサイトへのアクセス数は少しずつ伸び、アクセス自体は月間1000人程度ではあったものの、資料ダウンロードは月20件程度、問い合わせも4件程度発生するという流れをつくることができました。
この要因はWebサイトを単にアクセスを稼ぐ手段としてではなく、真の意味での「Web集客」のために利用し、「リアルの営業活動を楽にすること」と「見込み客から信頼を得るためのベースキャンプ」のためのツールとして活用したことにあるといえます。
まとめ
Web集客の本質は、単にアクセス数を増やすことではなく、質の高い見込み客を集めること、その見込み客に選んでもらうための情報を伝え関係構築のきっかけをつくることです。Webサイトはあくまで企業の営業プロセスの入口に過ぎません。
購入に至るまでには複数の接点での複数のアプローチが必要であり、各段階で適切なコンテンツやアプローチをすることが成功の鍵となります。
「すぐに結果を出したい」という気持ちはわかります。ですが、Web集客は短距離走ではなくいわばマラソンのようなもの。地道な取り組みを続けることが、大きな成果につなげるための近道といえます。